横井小楠殉節地
横井小楠殉節地(よこいしょうなんじゅんせつのち) 2009年12月10日訪問
この日は朝の散歩程度しか時間が取れなかったので、京都御所の東側のごく限られた範囲のみを歩いてみた。いずれ京都御苑内については時間をかけて見て行きたいと考えている。
京都御苑の南側を東西に走る丸太町通から寺町通を南に入り、下御霊神社に行く途中に横井小楠殉節地の碑が建つ。この碑は、その碑文より昭和7年(1932)に寄付を受けて京都市教育会が再建したことが分かる。中村武生氏の「京都の江戸時代をあるく 秀吉の城から龍馬の寺田屋伝説まで」(図書出版 文理閣 2008年刊)の中で説明しているとおり、京都市教育会は明治35年(1902)に創立した組織である。京都市の一部署でもなく、また似た名称の教育委員会とも関係がない。京都市の教育の普及と発達を図ることを創立の目的とし、現職の京都市長が会長や副会長を務める組織であった。理事や評議員には教育者や実業家が加わるなど、京都市の名士の集いという色彩が濃かったようだ。講演会の開催だけではなく、女子高等師範学校を京都に建設するように大臣に建議するなど、教育全般に関する提言も行ってきた。 大正4年(1915)11月、大正天皇の即位の大礼が京都で行われる。その記念事業として市内各所の志士義人等の古跡に標石を建てることとなった。建碑の基準として、国史教科書に掲載されているにもかかわらず、未だ標石のないものとし、60の候補を挙げた。古代から明治維新までの歴史の中で、著名な建物の址、偉人碩学の邸址、古址そして墳墓に分類し、法勝寺から薩摩・長州・土佐藩邸址が35、角倉了以から大久保利通や木戸孝充の邸址などが13、里程元標から佐久間象山、坂本龍馬の遭難の地が9、そして竹内式部、俊成卿、名和長年等の墓が3となる。この内、横井小楠が遭難した地も60の候補の中に含まれていた。中村氏によると、この内44基が大正3年(1914)から大正5年(1916)までの3年間に建立されたことが確認できている。つまり建立が予定されていた碑は、即位の大礼の記念事業として行われたのであろう。ただし横井小楠の最初の標石がいつ建立されたのかは不明である。
その後の大正時代、建碑は例外を除きほぼ行われず、寺井萬次郎によって再開されたのは昭和に入ってからのことだと中村氏は説明している。再建された横井小楠殉節地の標石も昭和の建碑の一つである。これは昭和天皇の即位の大礼が昭和3年(1928)11月に行われたこと、さらには明治維新後初めての戊辰が昭和3年であり、幕末ブームが再来していたことにも関係する。子母澤寛の「新選組始末記」が出版されたのもこの昭和3年である。
松平春嶽の政治顧問として越前藩に招かれた横井小楠は、藩政改革さらには幕府政事総裁職であった春嶽の助言者として幕政改革にもかかわるようになる。そして明治元年(1868)新政府にも参与として出仕している。例えば山脇之人の「維新元勲十傑論」(1884年刊)では、西郷隆盛、木戸孝充、大久保利通に始まり、次いで江藤新平、横井平四郎を挙げている。この後、大村益次郎、小松帯刀、前原一誠、廣澤兵助そして岩倉具視と続く。この人々は戊辰戦争を生き抜いた人物の中で、明治17年(1884)の執筆時に既に亡くなっている人物だけを10人採り挙げて十傑としている。序文において下記のように記している。
第一流ノ功臣ハ殆ント此ニ尽キ今日僅カニ残留スル者ハ大率第二流ノ士ノミニ止マラントス
第二の改革として民権運動が始まるその時期において、第一の改革である明治維新を懐かしみその偉大さを称えるために書かれたともいえる。そのため、ここには既に明治維新を見ずに斃れた吉田松陰、高杉晋作も坂本龍馬も、そして第二流と称された伊藤博文、板垣退助そして大隈重信も現われない。その代わりに前原一誠や広沢真臣あるいは大村益次郎を敢えて取り挙げなければならなかった事情もあるようだ。そのようなことを除いたとしても、維新当時の横井小楠に対する評価の高さは十分に分かる。
これに対して、現在の横井小楠に対する評価は極めて低迷している。例えばNHKの大河ドラマにおいても、横井小楠の出番はほとんど無かったといってもよいだろう。2010年の「龍馬伝」では坂本龍馬に多大な影響を与え、存在したか疑問の余地の残る船中八策の思想の基となったため取り上げられている。2013年の「八重の桜」でも松平春嶽にスポットライトが当たっているにもかかわらず、小楠の出番はついに無いようだ。「八重の桜」では春嶽の策士的な側面を際立たせる演出のためか、中根雪江や由利公正も現れない。
岩波書店 1971年刊
このように横井小楠が忘れ去られようとしている現状には、いくつかの理由がある。その中でも最大の要因は、現在の人々にとって儒教を基盤とした小楠の思想が理解し難いものになってしまった点ではないだろうか?当時、欧米諸国と日本との技術力の差を極めて正確に把握していた日本人の1人に佐久間象山がいた。単純な攘夷行動が日本を危うくすることを早くから知り得ており、日本が欧米の列強に飲み込まれないようにするためには、まずは国力を上げなければならないことを強く感じていた。そのため早期に欧米の技術を日本に移植する必要があると考え、積極的開国論を唱えている。そして和魂洋才と割り切った上で洋才の部分、すなわち欧米の先進技術を貪欲に追求していった。これは当時の日本における対外問題の解決策としては分かり易い方法であった。そのような経緯があるため、象山の最大の関心は欧米の技術に向けられ、常にその先に存在する「モノ」に視線が向けられていたともいえる。
しかし横井小楠の対外政策は、もう少し複雑である。まず目指すべき政治を「尭舜三代の治」に置いている。尭舜三代とは堯と舜の二人の聖天子と、それに続く時代の統治者、夏王朝の禹、殷王朝の湯王、周王朝の武王のことを示す言葉となっている。治国安民、利用厚生の面でも優れた政治が行われ、民衆の生活が安定した時代であったと考えられ、儒教的な理想世界となっている。
嘉永6年(1853)正月に横井小楠は「文武一途の説」を書いている。これはペリー来航以前の文ではあるが、既に来航が必至であることを知った上での著述とされている。「続日本史籍協会叢書 横井小楠関係史料1」(日本史籍協会 東京大学出版会 1938年刊 1977年覆刻)によると、この意見書は以下の言葉から始まっている。
有二文備一者必有一武備一と申して古の聖賢は大英雄大豪傑に在ましけり。
一見すると賢者が備えるべき徳について述べているようにも見えるが、外艦渡来が近づき次第に世論が威勢の良い武に偏るのを目にして発した警告である。
此説行はるゝ時は譬ば激剤を以て病毒を討つが如し、一旦に士気を張り一旦に奇功を奏るの勢あるは必定なれ共、元来仁義忠誠の心術を磨く正心誠意の上より推し本き来らざれば、其弊忽に生じ、或は客気麁暴の手荒き風とも成り、或は権変功利の拙き術とも流れて其末終に如何とも成し難き勢に落入るは鏡に懸て見るが如し。
小楠は武を廃すことを望んで「文武一途の説」を書いたのではない。これは応接にあたる者の心構えを説いた文であり、越前藩内の主だった人に回覧するように村田氏寿に送っている。武力を頼みとしている者が、外国との応接に当たることは予期せぬ戦争を派生させる可能性を秘めている。しかしそれ以上に小楠が恐れたことは、武に頼る者は武力では敵わないと知った時に無原則に妥協の道を選ぶことにあった。そのためには武だけでなく文武を兼ね備えた者が当るべきと考え、「文武一途の説」と名付けている。真の儒者は武にも秀でて大豪傑でなくてはいけないと最初に述べている。これが小楠の理想とする儒者の姿であり、また外交交渉を任すべき人物と考えている。
松浦玲編 中央公論社 1970年刊
嘉永6年(1853)6月3日、アメリカ合衆国海軍東インド艦隊を率いて浦賀に来航したペリーは、直接江戸において外交交渉を行うべく、江戸湾を北上する。このような高圧的な外交交渉に対して、多くの有志は幕府の無策な対応振りを批難するだけでなく、アメリカの示威行動に対して非を唱えた。もともと根源的に持ち合わせてきた攘夷思考に加え、ペリーの無道な行為に強い屈辱を感じたことが、その後の対外交渉をさらに困難なものにしたことは明らかである。
町田明広氏は、その著書「攘夷の幕末史」(講談社現代新書 2010年刊)で、攘夷思想の萌芽をアジア的な華夷思想(=中華思想)に見ている。中国を中心とする世界観においては、日本もまた夷狄のひとつである。そのため中国の文化・思想を学び、取り入れることで中国の華夷思想の中で冊封国となっていった。冊封とは中国王朝の皇帝が東アジアの夷狄君主に王や侯などの中国の爵号を授け君臣関係を結ぶことによって形成される国際秩序である。冊封体制内では、独自の交易方法である朝貢が行われていた。中国の皇帝は冊封国から上納された朝貢の何十倍もの恩賜を与えるため、単に東アジアにおける安全保障システムだけではなく、物々交換を超えた貿易に成り得ていたと考えられる。中国、朝鮮そして日本で行われてきた海禁(=鎖国)は冊封体制を維持する上で必要な政策でもあった。
中国を中心とする華夷思想の中に属していた日本も、次第に朝貢国を作り出すことで東アジアにおける新たな極となることを目指す。町田氏はこれを東夷の小帝国と呼んでいる。江戸幕府によって鎖国を維持するようになると、国学や水戸学を基にした尊皇攘夷思想が勃興する。国外情勢が分からない中で高まったナショナリズムのひとつの現われと考えてもよいだろう。
幕府はペリーとの交渉掛として、町奉行井戸覚弘とともに林大学(11代林復斎)を当てている。当然のことではあるが、この選考には小楠が「文武一途の説」で建言した文武兼備は考慮されていない。ただ漢文力を活かし中国との外交を家業としてきた林家の当主として選ばれている。これまでも小楠は自らが理想とする世界とは全く異なる現実に対して、日本の儒教の存在を認めず、強く否定している。そして小楠の提言にも係わらず、幕府は旧来の東アジア外交と同じ方法で難局に対応した。嘉永7年(1854)何等の原理原則を持たず交渉に臨んだ結果、下田・函館の開港や片務的最恵国待遇を含む神奈川条約を締結せざるを得なかった。
徳永洋 新潮新書 2005年刊


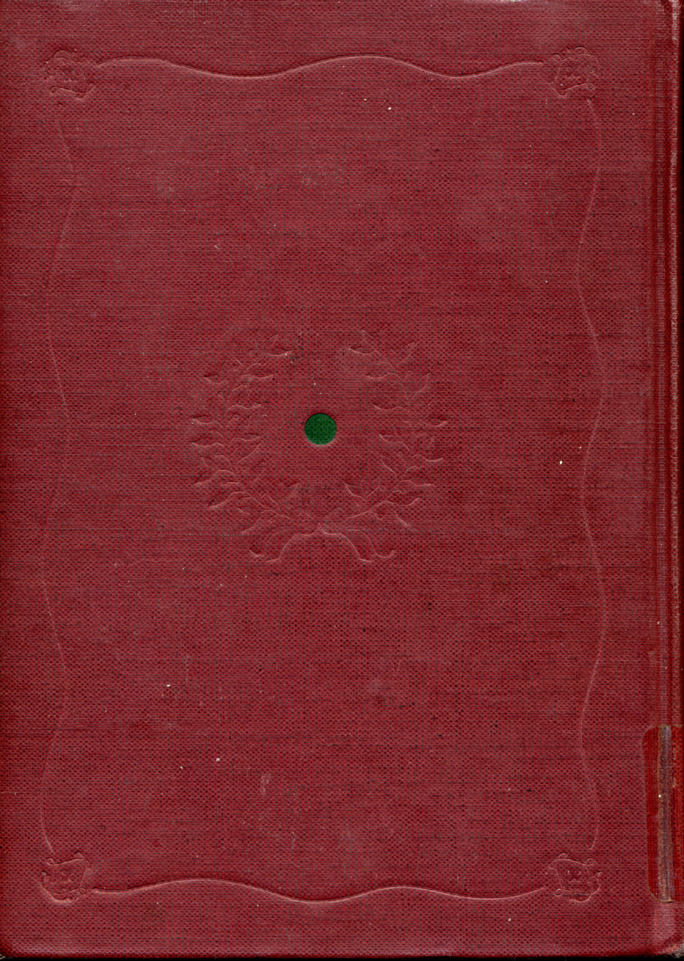
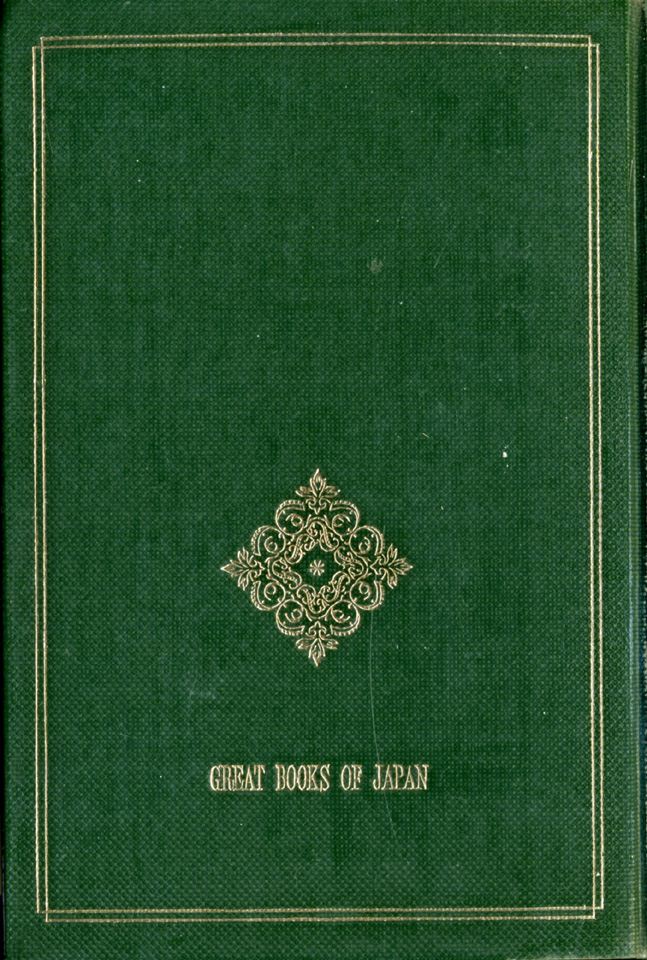
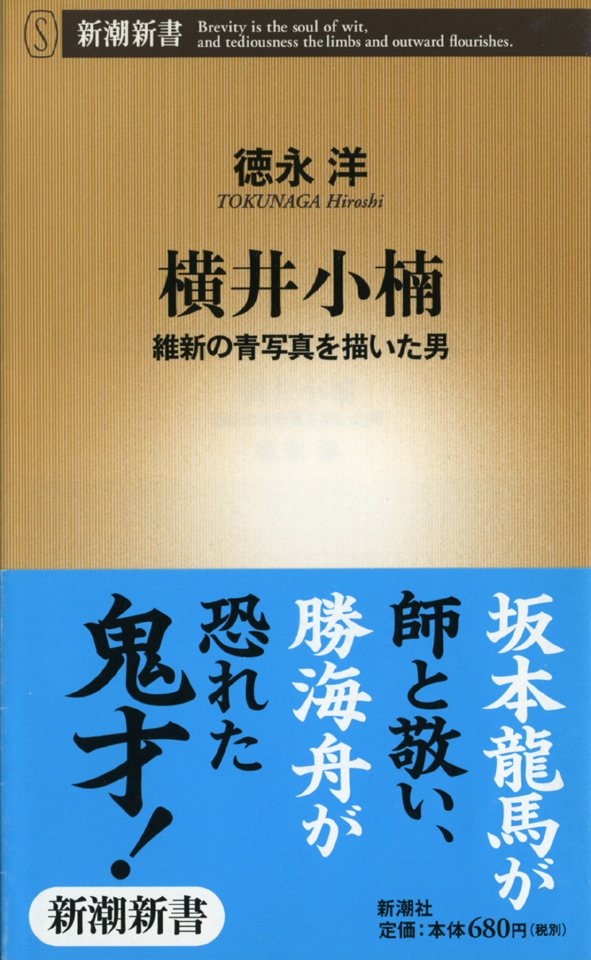

















































この記事へのコメントはありません。