京都御苑
京都御苑(きょうとぎょえん) 2008/05/13訪問
京都御所の参観後、京都御苑内を散策しながら、烏丸今出川の方向へ向かう。
幕末の京都御所周辺の状況は、国際日本文化研究センターに保管されている文久3年(1863)に作られた内裏圖を見ることで想像できる。この内裏圖の外周部には北に今出川通、南に丸太町通、西に烏丸通、東に寺町通が描かれている。現在の京都御苑の外郭線を収めた図であることが分かる。この地域の大部分の土地が公家の屋敷によって占められていた。京都御所、仙洞御所を除くほぼ全てが、今では想像できないが、大小の区画に分割され公家の邸宅が建てられていた。しかし明治2年(1869)天皇が東京へ移ると、冷泉家など除く大多数の公家は天皇とともに東京に移り住むこととなった。そのため公家屋敷も住み手がなくなり、次第に荒廃していった。明治10年(1877)京都に還幸された明治天皇がこの状況を目にし、京都府に御所の保存・旧慣を維持する御沙汰を下した。京都府は、直ちに公家屋敷を撤去に取り掛かり。外周石垣土塁工事、苑路工事を行い、樹木植栽等の内裏保存事業を開始し、明治16年(1883)当初の予定より早くに完了した。この後、御苑の管理は京都府から宮内省に引き継がれるが、整備は継続され、ほぼ現在の京都御苑の姿が整ったのは、大正大礼のために建礼門前大通りの拡幅改良等の改修工事が行われた大正4年(1915)のことであった。
終戦後の昭和22年(1947)京都御苑は、新宿御苑や皇居外苑とともに、国民公園とすることが閣議決定され、昭和24年(1949)厚生省の管理運営のもとに、由緒ある沿革を尊重するとともに、国民庭園として広く国民に開放し利用することとなった。さらに昭和46年(1971)7月、環境庁が発足すると、国民公園の管理は自然保護行政とともに環境庁に移り、従来からの御所の前庭としての景観維持や都市公園的な役割に加え、大都市の中の広大な緑地としての自然環境を保全し、自然とのふれあいを推進していくという新たな役割が重視されるようになった。
そのため現在、宮内庁の施設である京都御所、大宮御所と仙洞御所そして新たに作られた内閣府の施設である京都迎賓館を除く、京都御苑の管理は環境省が行っていることとなる。
現在確認できるところ、京都御苑には9箇所の御門と5箇所の切通しから入ることができる。京都御苑に残る御門は、南に堺町御門、西に下立売御門・蛤御門・中立売御門・乾御門の4つ、北に今出川御門、東に石薬師御門、清和院御門、寺町御門の3つで計9つとなる。これらの門は24時間開放されているため、もちろん閉庭時間はない。東西700メートル、南北1300メートルと広大な敷地であるため、苑路も一部生活道路と化している。
「京都御苑」 の地図
京都御苑 のMarker List
| No. | 名称 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|
| 01 | ▼ 京都御所 | 35.0241 | 135.7621 |
| 02 | ▼ 大宮御所 | 35.0224 | 135.765 |
| 03 | ▼ 仙洞御所 | 35.0206 | 135.7662 |
| 04 | ▼ 拾翠亭 | 35.0177 | 135.7617 |
| 05 | ▼ 閑院宮邸 | 35.0181 | 135.7601 |
| 06 | ▼ 京都御苑 堺町御門 | 35.0177 | 135.7631 |
| 07 | ▼ 京都御苑 下立売御門 | 35.0194 | 135.7595 |
| 08 | ▼ 京都御苑 蛤御門 | 35.0231 | 135.7595 |
| 09 | ▼ 京都御苑 中立売御門 | 35.025 | 135.7596 |
| 10 | ▼ 京都御苑 乾御門 | 35.0274 | 135.7596 |
| 11 | ▼ 京都御苑 今出川御門 | 35.0289 | 135.7623 |
| 12 | ▼ 京都御苑 石薬師御門 | 35.0277 | 135.7667 |
| 13 | ▼ 京都御苑 清和院御門 | 35.0232 | 135.7668 |
| 14 | ▼ 京都御苑 寺町御門 | 35.0199 | 135.7669 |







































































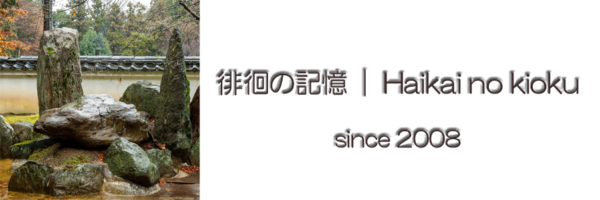

この記事へのコメントはありません。