修学院離宮 その4
修学院離宮 (しゅがくいんりきゅう) その4 2008年05月20日訪問
一番高台にある隣雲亭の見学の後は、雄滝の方向に下っていく。緑の濃いこの時期、木立の奥にある雄滝の姿ははっきりとは見えないが、轟々とした水音が静かな離宮の中に響く。
そのまま浴龍池の東側を進む。中島と万松塢の間に架かる千歳橋が再び見えてくる。隣雲亭から見える千歳橋は非常に象徴的ではあるが、余りにも中国風なため周りとの調和が成されていないようにも見えた。社団法人土木学会関西支部の公式HP内には橋梁として千歳橋(http://www.civilnet.or.jp/gallery/bridge/kyoto/html/chitose.html : リンク先が無くなりました )の説明が掲載されている。切石積の橋脚の上に大きな屋根をもった建物が載せた形状は、橋殿と呼ぶべきものかもしれない。隣雲亭から降りてきた位置で千歳橋を見ると、左右対称には作られていないことに気付く。万松塢側は外側に張り出して腰掛けが設けられた四阿風、中島側は天皇の乗り物・鳳輦をイメージしたもので、屋根に鳳凰が載せられている。この橋は後水尾上皇の時代にはなく、文政7年(1824)に内藤信敦が床部分を、文政10年(1827)に水野忠邦が屋形部分を寄進したものである。これは光格天皇の行幸のために寿月観や隣雲亭の再建が成されたのと同時期のことである。現在では良くも悪くも修学院離宮を代表する景観になっている。
木橋の楓橋を渡り中島に入ると、目の前に窮邃亭が現れる。窮邃亭は修学院離宮において創建当時のまま残る唯一の建築。三間四方で柿葺宝形造の屋根を持つ。内部は18畳1室であるが、北の隅の6畳分が高くなっているため、上段として使われたのであろう。この場所からは西の浴龍池、北の三保ヶ島が眺められるように思える。参観時は西の突上げの板戸が一枚のみ明けられた状態なので確認できないが、西和夫著「京都で「建築」に出会う」(彰国社 2005年)には、板戸を外すと開口部の大きな開放的な空間となった窮邃亭の写真が掲載(P52)されている。そして敷居の高さも低く抑えたのは、窓際に座り、肘を着いて外の景色を見ることを考えて造られているためであろう。南の土間庇の軒下には、後水尾上皇宸筆による窮邃の額が懸かっています。
板戸が閉められている時の窮邃亭は、軒の出の浅い宝形の屋根を持った寺院建築のようにも見える。これらが開け放たれると隣雲亭と同様に展望を目的に建てられた建築であることが分かる。
中島より新しく架け直された様に見える土橋を渡り、浴龍池の畔に出る。ここより舟屋、御舟着を見ながら、浴龍池の西浜に出る。この土手からは西には棚田越しに京都市街地の北部、そして東には浴龍池とその背後の比叡山が見える。
広角レンズで撮影した写真なので左手の白い煙突が小さく写るが実際はもう少し大きく感じる
「修学院離宮 その4」 の地図
修学院離宮 その4 のMarker List
| No. | 名称 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|
| 01 | ▼ 修学院離宮 上離宮御成門 | 35.0538 | 135.8032 |
| 02 | ▼ 修学院離宮 上離宮隣雲亭 | 35.0539 | 135.8036 |
| 03 | ▼ 修学院離宮 上離宮雄滝 | 35.054 | 135.8037 |
| 04 | ▼ 修学院離宮 上離宮中島 | 35.0552 | 135.8035 |
| 05 | ▼ 修学院離宮 上離宮万松塢 | 35.0547 | 135.8031 |
| 06 | ▼ 修学院離宮 上離宮三保ヶ島 | 35.0556 | 135.8035 |
| 07 | ▼ 修学院離宮 上離宮窮邃亭 | 35.0551 | 135.8036 |
| 08 | ▼ 修学院離宮 上離宮千歳橋 | 35.0549 | 135.8033 |
| 09 | ▼ 修学院離宮 上離宮楓橋 | 35.0552 | 135.8037 |
| 10 | ▼ 修学院離宮 上離宮土橋 | 35.0553 | 135.8033 |





















































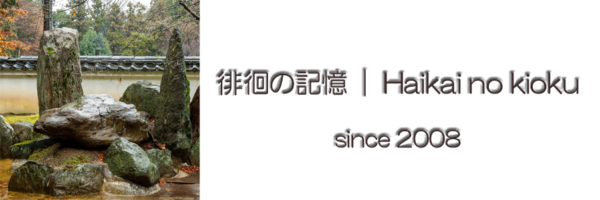

この記事へのコメントはありません。