横井小楠殉節地 その2
横井小楠殉節地(よこいしょうなんじゅんせつのち)その2 2009年12月10日訪問
横井小楠殉節地では碑の建立の経緯と、横井小楠が嘉永6年(1853)に建言した「文武一途の説」を通じて、小楠の思想がどのようなものであったかを記してみた。小楠の外交に対する考え方が少し長くなってきたため、翌年の再訪を約してペリーが日本を去ったところで前項を閉じた。この項ではペリーに次いで日本を訪れたプチャーチンへの応接を通じてさらに小楠の外交政策の展開を見て行く。
ペリーの1回目の浦賀来航から僅かに遅れ、嘉永6年(1853)7月18日、プチャーチンは旗艦パルラダ号以下4隻の艦隊を率いて長崎に来航している。幕府の定めた外交交渉の方法に従い、長崎奉行の大沢安宅に国書を渡し、江戸から幕府の全権が到着するのを待った。しかしクリミア戦争に参戦したイギリス軍が極東のロシア軍を攻撃するため艦隊を差し向けたという情報を得たため、11月23日長崎を離れ一旦上海に向かっている。
プチャーチンは同年12月5日再び長崎に戻り、幕府全権の川路聖謨、筒井政憲と計6回の会談を行う。交渉はまとまらなかったが、将来日本が他国と通商条約を締結した場合にはロシアにも同一の条件の待遇を与える事などで合意する。嘉永7年(1854)1月8日、一定の成果を得たプチャーチンはマニラへ向かい日本を去っていった。
プチャーチンの一度目の来航の知らせを聞いた横井小楠は、再び外交についての意見書として「夷虜応接大意」をまとめている。「続日本史籍協会叢書 横井小楠関係史料1」(日本史籍協会 東京大学出版会 1938年刊 1977年覆刻)によると下記のような言葉で書き出している。
我國の萬國に勝れ、世界にて君子國とも稱せらるゝは天地の心を躰し仁義を重んずるを以て也。されば亞墨利加・魯西亞の使節に應接するも只此天地仁義の大道を貫くの條理を得るに有り。此條理貫かざれば、和すれば國躰を損ひ戦ば破れ、二つのものゝ勢眞に顕然たるは更に又云に不レ及事也。凡我國の外夷に處するの國是たるや、有道の國は通信を許し無道の國は拒絶するの二ツ也。有道無道を分たず一切拒絶するは天地公共の實理に暗して、遂に信義を萬国に失ふに至るもの必然の理也。
最初の一文、日本国は仁義を重んじる国であるために君子国として世界の中でも勝れている、とするのは当時の一般的な見方と考えてよいだろう。その上で小楠は外交に、“天地仁義の大道を貫くの條理”を以って行うことを主張している。これなくして条約を結べば国体を損ない、戦えば敗れることが必定と観ている。そして鎖国の維持を主張するのではなく、開国の条件を提示している。それは有道の国とは通信を行い、無道の国に対しては拒絶の姿勢を以って対応するということである。
既にペリーによる高圧的な外交交渉を知った小楠は、外国応接の方法を下記のように具体的に記している。
今の世にあたり外虜に接する事を談ずるもの大抵四等あり。我宴安に溺れ彼威強に屈し、和議を唱ふるものを最下等とす。鎖国の舊習に泥み、理非を分たず一切に外國を拒絶して必戦せんとするは宴安に溺るゝの徒に増るといへども、天地自然の道理を不レ知して必敗を取るの徒也。又彼が無禮を悪み彼と戦んと欲すれども、我國貳百五十年の泰平に天下の士気頽廃して皆驕兵たるを憂へ、暫く屈して彼と和し其間暇を以士気を張り國を強して後彼と戦わんとのみ思ふは、彼是の國情を詳かにし利害の實を得たるに似たると云へども、其實は天地の大義に暗きのみならず利害に於ても亦決して其見處の如くなる事不レ能なり。廟堂假初にも彼と和する心ある時は天下の人心彌益惰弛に趣、士気何れの日か振起すべき。器械に到りても決して整の日あるべからず、三令五申其益無きのみならず天下遂に瓦解土崩の勢をなす事必然なり。然れば今日に當りて必戦の計を決して幕府列國材傑の人を挙用るの道第一の緊要とす。其人挙る時は其政改り、天下の人心大義の有事を知り士気一新するも瞬息の間に有て、今日の驕兵忽変じて精兵となる事猶手を復すに異ならず。
松浦玲 朝日新聞社 1976年刊
小楠は応接についての4つの方法を述べている。最も下策であるのは、相手の威権に屈し和議を申し入れること。これは神奈川条約に屈した徳川幕府の姿を予見している。それに次ぐのは理非を分かたず一切の外交を拒絶し戦争に導くもの。これは長州による下関戦争や攘夷主義者の無謀な殺害行為、すなわち小攘夷をも含んでいる。三番目にしばらく屈し和し、後に士気を張って戦うというもの。外国の先進の技術を積極的に取り入れ、国力の向上が図られた暁には再び鎖国を敷くという考えである。当時は二番目の小攘夷に対して、もう少し奥の深い策として大攘夷とよばれるものである。一見すると国情を理解し理知的な対応にも思えるが、天下の大義に暗い者の考えで、一度屈した士気は二度と戻らないと小楠は切り捨てている。最後の上策は、必戦の覚悟を固めた上で、幕府諸藩は優秀な人材を登用し政治改革を断行すること。これにより天下の人心は一新し、大義のあることを知ると考えている。それまでの三策とは異なったレベルで、正に政治改革への提言である。為政者を刷新することで、それまでの因循姑息な政策を破棄する。そして原理原則に基づいた政治目標を掲げることで、新しい政治が開かれると考えたのであろう。
横井小楠の「文武一途の説」と「夷虜応接大意」を攘夷論と見るか、開国論と見るかは意見の分かれるところである。「夷虜応接大意」において小攘夷も大攘夷も否定していることは確かである。しかし最上策として政治刷新が必要だと述べたものの、鎖国維持か開国なのかについては触れていない。「夷虜応接大意」の後半部分には下記のような記述が見られる。
我國毫も彼が強梁を恐れず、大義を明らかにして彼を拒絶せば夷虜不レ戦して畏服せざる事能はさる也。内を治め外を固くし軍艦守備を整へ或は通信通商のさまの事は別に論ずる旨ありて爰に混ぜず、今只彼に應接するの大義を述るのみ也。
無道なアメリカに対してロシアは有道の国であると、小楠が期待していたようである。魏源が著わした「海国図志」を小楠が読んだのは安政2年(1855)の頃と考えられている。そのため「文武一途の説」や「夷虜応接大意」を記した嘉永6年(1853)の時点では、体系だった欧米の情報は小楠の元には無く、世界の動向についても明るくはなかった。それにも関わらず上記のようなことを記したのは、幕府の制止を無視して江戸湾を北上したペリーとプチャーチンの交渉態度を比較しての印象論に依っていたと思われる。小楠は、戦争を覚悟した上で無道の国に対しては先ずは通信通商などを拒絶することを力説しているものの、「天地有生の仁心を宗とする國は我も又是をいれ」とし、国交を結ぶべき条件をここに示している。
松浦玲 朝日新聞社 2000年刊
ペリーは翌年に再訪することを約して去り、幕府は次の来航までに日米和親条約(=神奈川条約)を締結すべきか検討する時間を得ていた。小楠は無道の国、すなわちアメリカとの条約締結は拒否すべきと考え、その結果によって戦争が起きることも覚悟している。このアメリカとの開戦以前にロシアと条約を結ぶことが開戦準備と言われないために、ロシアとの条約締結を延期することをロシアに対して説明し理解してもらうべきだと主張している。すなわち嘉永6年(1853)の年末時点では、どの国とも国交を開くべきでないとしている。この結論を見る限り、小楠の意見書から見えるものは攘夷論ではなくても、積極的開国論でないことは明白である。
この「夷虜応接大意」における有道の国という条件付きの開国に、小楠の思想的な転換があったと指摘する人々は多い。源了圓氏は「公共する人間3 横井小楠 公共の政を首唱した開国の志士」(東京大学出版 2010年刊)において、「小楠はまだ攘夷論者であったが、しかし理論の上ではすでに開国論者であったと言わなければならない。」と述べ、三上和夫氏も「横井小楠 その思想と行動」(吉川弘文館 1999年刊)で、「この意見書からは、小楠の攘夷論から開国論への芽生えがはっきり認められるわけである。」としている。
それに対して松浦玲氏はその著書「横井小楠」(ちくま学芸文庫 2010年刊)の中で、横井小楠の思想は攘夷と開国の間を左右したのではなく、嘉永6年(1853)より一貫として有道の国とは結ぶという原理に変更はなかったとしている。この著作は1976年に「横井小楠」(朝日評伝選 1976年刊)として出版されてから、2000年に「横井小楠―儒学的正義とは何か」(朝日選書 2000年刊)として装いを代え、さらに2010年に増補を加えている。そのため、ちくま学芸文庫版「横井小楠」は松浦氏にとって、小楠研究の集大成であり、最新の資料を基に書かれた書籍と考えても良いだろう。
ここでは他の研究家の「いつの時期から横井小楠は開国論を展開したのか?」という上記のような見方とは一線を画している。確かに松浦氏に従うならば、横井小楠の嘉永6年(1853)から安政2年(1855)にかけての思想的な一貫性に揺るぎがなくなるし、幕府が成し得なかった政治的な大方針をこの時期に定めたことが明らかになる。しかしその反面で後期水戸学の攘夷論の影響下にあった小楠が、どの時点でその呪縛から離脱できたかを明らかにすることが出来なくなる。徳川斉昭の幕政参画を過大評価あるいは誤解した小楠は、一時は斉昭に期待してしまう。しかし嘉永7年(1854)の神奈川条約締結を知り、斉昭に失望の念を抱いたのが水戸学からの離脱の契機となったと松浦氏は述べている。しかし実際には「夷虜応接大意」を記した時期より思想的な離脱は始まっていたように思われる。恐らく水戸藩を頼ることが困難な状況を確認できたのが嘉永7年であり、その行き詰まり状況を感じ始めていたのはそれより以前のことであっただろう。攘夷論の影響下にあった横井小楠を一度認めなければ、それを超越する思想の萌芽が見えなくなると考える。
松浦玲 ちくま学芸文庫 2010年刊


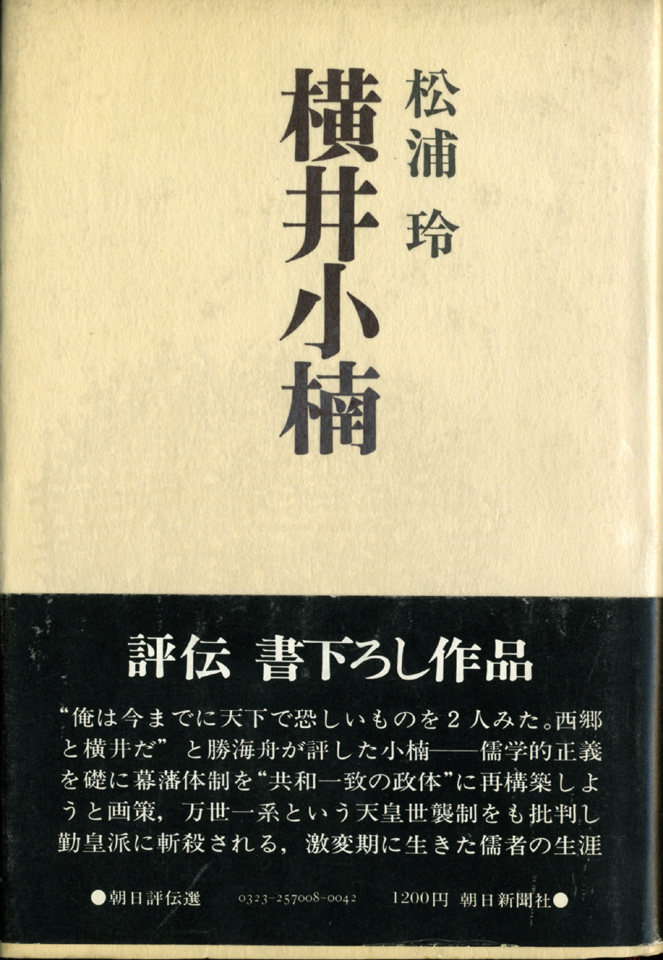
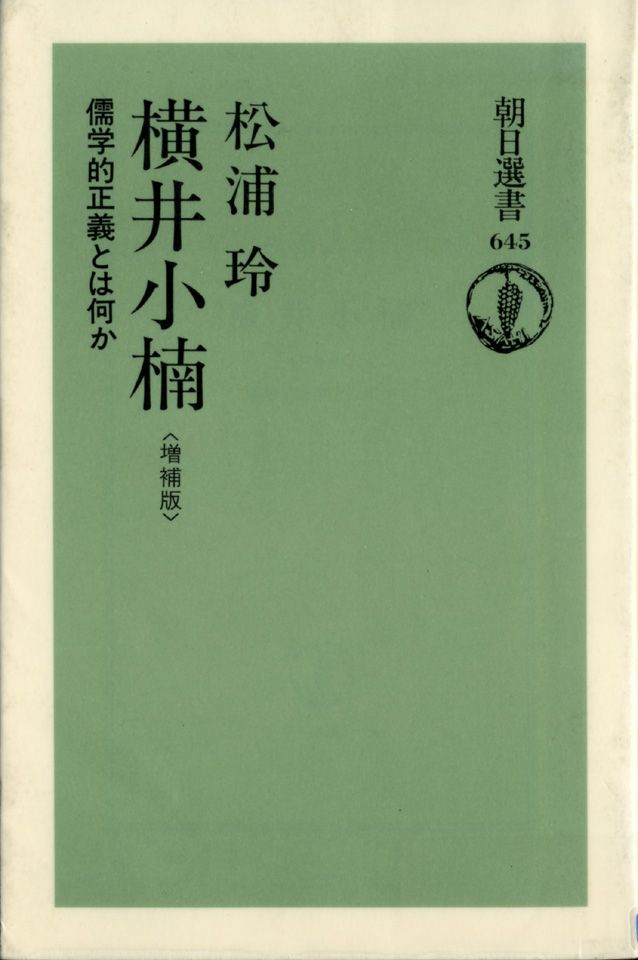


















































この記事へのコメントはありません。