東福寺 龍吟庵 その4
東福寺 龍吟庵(とうふくじ りゅうぎんあん)その4 2009/11/28訪問
東福寺 龍吟庵 その3では、一条実経が無関普門禅師を東福寺に招いたところまで記した。ここからは亀山上皇と無関普門とのことに記してみる。
弘安の役終結後の正応2年(1289)亀山上皇は離宮禅林寺殿で落飾し、法皇となっている。虎関師錬が記した南禅寺の由来書「文応皇帝外紀」によれば、この当時の離宮には怪異な事が頻繁に生じていた。法皇は、高僧の徳を以って収めるしかないと考え、奈良西大寺の叡尊上人を迎えている。しかし、叡尊の法力を以ってしても、怪は退散しなかったため、次に無関禅師が召される。禅師は護摩を焚いたり呪文を唱えるでなく、雲衲と共に離宮に留まり、坐禅、掃除、勤行と、禅堂そのままの生活を送られる。これにより遂に怪異現象は鎮まる。
虎関師錬は、既成の宗教(叡尊は真言律宗の僧)に対する、臨済宗の優位性を述べる例として、上記のような逸話を記したと思われる。叡尊は弘安4年(1281)蒙古襲来に際して、亀山上皇の御幸を西大寺に迎え、石清水八幡宮で尊勝陀羅尼を読誦している。また弘安7年(1284)宇治橋修造の朝命を受け殺生禁断のために宇治川の網代を破却し、弘安9年(1286)宇治橋が修築すると、橋南方の浮島に十三重石塔婆を建立するなど勧進修造活動にも活躍した鎌倉時代中期を代表する高僧である。そして上記の逸話のすぐ後の正応3年(1290)西大寺で病を発し秋には示寂している。享年90。
正応4年(1291)亀山上皇が離宮禅林寺殿を南禅寺に改め、無関普門禅師を開山として迎えるが、禅師は病を得て東福寺に帰山せざるを得ない状況になる。禅師の病篤きことを知った法皇は、龍吟庵に禅師を見舞い、数日間駐輦され自ら看護したとされている。病態がいよいよ重くなるや、禅師は
来無所在 去無方所 畢竟如何 喝 不離当処
という遺偈をしたため、12月12日に龍吟庵で遷化されている。享年80。「大明国師行状記」によれば、遺骸は庫裏の背後の慧日山龍吟の丘にて火葬に付され、遺骨は銅製の骨蔵器に納め、石櫃に入れられ埋葬されたとされている。「古寺巡礼 京都 18 東福寺」(淡交社 1977年刊)には、龍吟庵蔵で東京国立博物館寄託の重要文化財・大明国師(無関普門)銅骨蔵器(一合)の写真が掲載されている。一面緑青に覆われた円筒形の骨蔵器の側面には、「正応四年十二月十二日于時東福禅寺師霊骨龍吟補口」の銘が施されている。文化庁の国指定文化財等データベースに掲載されている「銅無関禅師骨蔵器」によると、骨蔵器は昭和36年(1961)龍吟庵の庫裏の北側にあった石造無縫塔の国師の墓の石室内で発見されている。この墓は寛政3年(1791)の五百遠忌に際し、境内の某所から移築した記録があるため、骨蔵器の発見後に同塔下を発掘調査した結果、地下2メートルより花崗岩製の石櫃を出土している。石櫃の中より骨蔵器を発見した訳ではないため、両者の関係は確実でなく、骨蔵器を大明国師の骨壼と特定することはできないようだ。しかしながら寛政以後は禅師のものと信じられ、旧埋納地より持ちきたった永仁2年(1294)銘の経筒と共に、石室内に納められたものと考えられている。 骨蔵器は鋳銅製被蓋造りの丈の低い円筒状で、蓋には緩い甲盛りがあり、鈕はない。何の飾り気もない簡素なもので、禅宗高僧の骨蔵器に相ふさわしいものともいえる。また花崗岩製の石櫃は、蓋も身もほぼ同じ大きさの箱形で、身には骨蔵器を納める深い円形の孔を穿ち、蓋は印籠蓋様に作られている。骨蔵器及び石櫃の重要文化財指定は以下のようになっている。
1 銅骨蔵器 一合
2 錫外筒
(寛政二年大□(明)国師五百□(遠)忌在銘) 一合
3 石櫃 一合
4 金銅経筒
(永仁弐年三月十五日行願在銘) 一合
5 須恵器合子
(竜吟庵無関禅師墓納置) 二合
昭和50年(1975)方丈の北側に、鉄筋コンクリート造の開山堂が建立されている。扁額「霊光」「勅諡大明国師」は足利幕府第3代将軍足利義満の筆によるもので、准三宮、道右および天山という印刻が見られる。堂内には、重要文化財に指定されている大明国師坐像が安置されている。檜材の寄木造りで、玉眼を嵌入し、彩色が施されている。国師の肖像としては、南禅寺に二幅、天授庵に一幅があり、いずれも重要文化財に指定されているが、彫像としては恐らく現存唯一の遺例と考えられている。山形に垂れた上瞼、大きな耳などの風貌は、上記の肖像と良く一致する。また、右側の瞳を外側に反らして斜視にし、眉や目尻に痘痕を、眼と唇の下には疣を表現するなど、国師の遺風を弟子たちに伝えるために作成された写実性の高い彫像である。躰部の肉付けも自然で、良く鎌倉後期の特色を示している。制作年代は、国師の入寂された正応4年(1291)か、嘉元元年(1303)に行なわれた十三回忌の法要までの間と推定されている。
昭和38年(1963)修理が行なわれ、像内から以下のような納入品が発見される。
1 木製五輪塔(水輪水晶製
内に金製舎利容器を納める) 一基
2 緑瑠璃舎利壺 一口
3 錦袋 二枚分
4 版本諸尊図像陀羅尼(九重守
弘安八年二月十五日信聖刊記) 一巻
5 紙本墨書六尊種子 一紙
6 古写経断片 四片
7 香木 一片
8 銅環 一箇
9 銀箔 三枚分
10 木箱 一合
11 木製五輪塔 一基
12 紙本墨書国師像内仏舎利之記
(寛政元年奥書) 一帖
この木造大明国師坐像を安置した壇下を半地下壕とし、その中に国師の墓石とする石造無縫塔及び国師の遺骨を納めた銅骨蔵器を納めた石櫃が安置されている。
南禅寺は正応5年(1292)に上皇によって選任された第二世規庵祖圓禅師(南院国師)によって伽藍造営が始められたため、無関普門禅師の南禅寺住持としての期間があまりにも短いため開山としての業績が残されなかった。しかし暦応2年(1336)虎関師錬禅師が南禅寺第15代住持に就任すると、朝廷に上奏し開山塔建立の勅許を請うている。光厳上皇の勅許を得るとともに、塔を霊光、庵を天授と名付ける勅状を賜り、翌暦応3年(1337)に開山塔の建立がなされ、天授庵が開創した。無関普門禅師の死去から46年の後のことである。

























































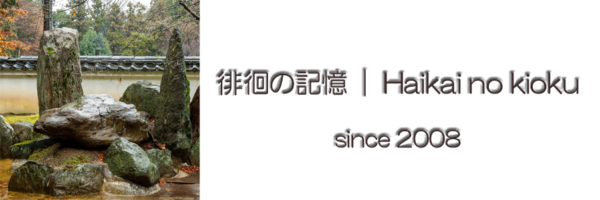

この記事へのコメントはありません。