錦市場 その2
錦市場(にしきいちば) 2008/05/14訪問
錦市場 有限会社 魚力 焼き魚
錦市場は鎌倉時代以降は商工業街として発展した。室町時代には、酒屋をはじめとする多種多様な職種が存在した。しかし文明年代(1469~1486)に応仁の乱により錦小路も衰退する。再興されたのはおよそ100年後の天正年代(1573~1593)のことであった。
錦小路が魚鳥の市場となったのは豊臣秀吉の天下統一後と考えられている。この地の人口が多いこと、御所への納入が容易であったこと、そして清く冷たい地下水が涌き出ることが、この地に市場が生まれるもととなっている。
錦市場の公式HPによると本格的な魚市場となったのは江戸時代に入ってからである。元和年間(1615~1623)幕府より魚問屋の称号が許され、万治・寛文(1658~1672)の頃、上の店、錦の店、六条の店の3ヶ所が最も繁栄を極め、三店魚問屋と呼ばれた。特に錦小路の商人は、公儀から鑑札を得ることにより独占的な営業が行われていた。明和7年(1770)錦小路高倉に青物立売市場が奉行所により認められ、安永8年(1779)魚問屋のそばに野菜の市場が開かれた。
明治維新とともに三店魚問屋の特権も廃止され、魚問屋も自由に営業されるようになった。同業者間の競争が激しくなり、倒産する店が相次ぎ、明治16年(1883)頃には7店程になったとも言われる。同業組合等を設けることで過度の同業競合を避け、再び繁栄を取り戻すことができた。
昭和2年(1927)に下京区朱雀分木町に京都中央卸売市場が開設されたことで、錦の卸売業者の多くも移転した。錦小路に残った店と新しく入った店々の協力により、戦後の移り変わりの激しさにも耐え、錦小路は京の台所の位置付けを守ってきた。
錦市場 錦もちつき屋 つきたてのお餅・豆もち・大福もち・おぜんざい・宇治金時
錦市場 桝悟本店 京漬物
錦市場 三木鶏卵 だし巻玉子・温泉玉子・生玉子他
錦市場 田中鶏卵店 京風だし巻・卵加工品
錦市場 錦 大友 乾物
錦市場 島本海苔乾物株式会社 寿司海苔・諸乾物・椎茸・花かつを・和食料理用諸材料
錦市場 不二食品 佃煮・惣菜
錦市場 野村佃煮・錦小路店 看板商品の「舞扇」を中心に「ちりめん山椒」や「蕗しぐれ」など
錦市場 竹長 日本海の塩干物を扱う
錦市場 京丹波 「焼ポン」は厳選された国内産の栗を特殊圧力製法で、ふっくらと焼き上げる
錦市場 湯波吉 寛政2年の創業以来、最良質の大豆で製造する湯波
錦市場 のとよ 炭焼のうなぎ、川魚
錦市場 豆招福 豆と干し芋
錦市場 錦 高倉屋 京漬物

















































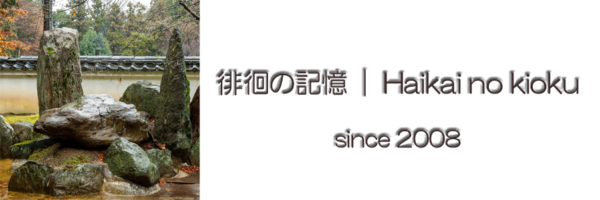

この記事へのコメントはありません。