大徳寺 孤篷庵 その4
大徳寺 孤篷庵(こほうあん)その4 2009年11月29日訪問
大徳寺 孤篷庵で、小堀政一と春屋宗園や江月宗玩との関係について書いてみた。また、大徳寺 孤篷庵その2、大徳寺 孤篷庵その3で政一の仕事の中の建築と作庭を中心に眺めてきた。比較的長く書いてみたものの、茶の湯については触れていないので、遠州芸術の全体像を紹介することにはならない。それでも寛永文化を代表する人物の一人であり、遠州好みを生み出す背景となったものの一端が伺えるものとなった。
ここでは、非公開となっている孤篷庵の建築について資料等を参照しながら書いてみる。
大徳寺 孤篷庵の最初に記述したように、慶長17年(1612)小堀政一は大徳寺塔頭の龍光院内に親交のあった江月宗玩を開祖として小庵・孤篷庵を建立している。そして30余年経た寛永20年(1643)に現在の地に移すが、寛政5年(1793)の火災により焼失している。松江藩主の松平治郷(不昧公)が古図に基づき再建している。そのためか、現在の孤篷庵の本堂、書院、そして茶室の忘筌は、有名であるのにもかかわらず、明治36年(1903)に重要文化財に指定されるに留まっている。本堂は、桁行七間、梁間三間、一重、入母屋造で桟瓦葺。寛政9年(1797)以前の建立で、雲林院客殿を移築したものとされている。書院は、桁行六間、梁間六間、一重、右側面入母屋造、左側面切妻造で桟瓦葺。寛政11年(1799)の棟札がある。そして忘筌は桁行四間、梁間三間、一重、切妻造の桟瓦葺。
GoogleMapを基にして作成した配置図上で、赤い四角の部分が本堂、その西北角の橙色の部分に忘筌がある。ここで注意すべき点は本堂の建物内に忘筌が収まっていないことである。本堂の北側には小さな中庭を挟んで庫裏が建てられている。そして本堂と庫裏の西側には、青い四角で印した書院が、やはり庭を挟んで建てられている。この書院には西南に直入軒、西北に山雲床が作られている。なお山門から本堂玄関に向かって美しい延段が造られているが、その中間のあたりに延段を横切る溝が切られている。これは山門から眺めても気になる箇所であった。意匠的に造られたものではなく、恐らく本堂の北側に作られた中庭に落ちる雨水の排水用として作られたものと考えられる。主だった3つの建物以外にも、いくつかの屋根が見えるため、非常に複雑な構成となっている。
孤篷庵の本堂と書院の構成は、宮元健次氏の著書「[図説]日本庭園の見方」(学芸出版社 1998年刊)や「日本の建築空間 新建築2005年11月臨時増刊」(新建築社 200年刊)などに掲載されている平面図によって確認することができる。ネット上で孤篷庵の図面を閲覧するならば、下山眞司氏のブログ 建築をめぐる話・・・・つくることの原点を考えるに、「日本建築史基礎資料集成 二十 茶室」から転載した平面図と修理工事報告書からの断面図を参照するのがよいと思われる。
小堀遠州が創った茶室忘筌の名は荘子外物篇にある下記の文が由来となっている。
筌は魚に在る 所以、魚を得て筌を忘る。
蹄は兎に在る 所以、兎を得て蹄を忘る。
言は意に在る 所以、意を得て言を忘る。
吾、安にか夫の忘言の人を得て、之れと与に言わんや。
臨済禅 黄檗禅 公式サイトには、忘筌の意を詳しく説明している。
もともと筌は「うえ」とよばれ、細い割竹で作った魚を捕らえるための道具を指し示している。蹄も兎などを捕らえる「わな」のことである。川に仕掛ける筌は、魚をとるための道具であり、魚をとってしまえば、もはや用のないものとなるという意味である。そして言葉は意を伝える手段でしかないということを付け加えている。何が目的で、何が手段なのか、間違いのないように注意しなければならないという教訓を与えている。
この忘筌に至る道筋を図面上から辿ってみる。先ず孤篷庵の空堀に架かる中国趣味の石橋を渡り、山門を潜る。左側には刈り込み、そして右側には樹木の奥に庫裏と本堂とそれを囲む塀が見える。そして中央に、あまり見慣れない赤土の上に、美しくデザインされた直線状の延段はアイストップとして植えられた松に向かい南へ続く。孤篷庵の塀には、この地面の赤土に合うように黄色の土を使用している。延段は長めの縁石を左右交互に配置し、それ以外を不整形な石を敷いている。このリズム感が非常に良く出ている。庫裏への敷石が延段から分れた先に、細い排水溝が右側の建物から始まり、延段を分断して左の刈り込みの中へ入って行く。本来ならば竪樋と同じように見せたくないものであるが、長い道行きの中間の良き目印としている。正面に配置された松の手前で延段は90度折れて本堂玄関へと向かう。今まで直線状の縁石を使用してきたが、この屈曲部で初めて緩やかな曲線で抉った縁石を使っている。この石により来訪者は右手の玄関へと優しく誘導される。なお山門から続いてきた延段の先には塀の一部を刳り貫いたように見える外待合が設けられている。この外待合へは、手前の松を回り込むように延段から飛石が配されている。
玄関を入り、そのまま本堂の南広縁に上がる。広縁の先には、広縁と並行に作られた背の低い生垣があり、その先は苔地も白砂も石もない、ただの赤土の方形の庭が広がる。つまり本堂南庭は、山門からの続く路地と同じく赤土の庭となっている。庭の先には2段の生垣が本堂と並行に植えられている。そして刈り込みの中には何本かの木々が見える。本堂を船に見立て、2段の生垣は打ち寄せる波を表現しているとされている。現在は見えないものの、波の先には船岡山の頂が見えたであろう。
孤篷庵の庵号の「孤」はひとり、「篷」は菅や茅などを粗く編んだ筵のことであり、和船を覆って雨露をしのぐのに用いることから苫舟を意味している。小堀政一は天正7年(1579)近江国坂田郡小堀村(現在の滋賀県長浜市)の土豪・小堀正次の長男として生まれている。生国である近江にある琵琶湖に浮かぶ「一艘の苫舟」とは遠州自身のことである。孤篷庵で用いられている赤土は、近江国の暖かく優しい風土を表現するために用いられているとも言われている。
本堂から南庭を眺めると左手に編笠門が見える。これは小堀家の墓地へ続く門である。また南庭右手(西側)には、やはり赤土の上に築いた枯山水の庭、近江八景の庭が広がる。この庭は、忘筌の先に続く書院の直入軒の縁から延びる渡り廊下から観賞するように造られている。この蹲のある角を琵琶湖に突き出した釣殿に見立て、手前の低い松をこちら岸、その先に広がる赤土の庭を琵琶湖として観賞したのであろう。この西に面した庭は西日を受けると更に赤味を帯び、遠州にとって故郷である琵琶湖の夕景を呼び起こすものであった。
孤篷庵の本堂は、一見すると禅宗の方丈建築の様式に沿っている。一般的な方丈は東福寺 龍吟庵などに見られるように南に広縁、それ以外の3面にも縁を巡らせた上で、南北に2列、東西に3列の六室で構成されている。南に面した3室は、西に檀那の間、中央に室中、東に礼の間。そして北に面した3室は、西に住持(衣鉢)の間、中央に仏間、そして東に書院の間を配することが一般とされている。孤篷庵の場合、広縁が南面と東面の2面のみとなり、檀那の間の縁は室内化され西檀那の間のような扱いとなっている。そして忘筌は、本来ならば日常起居する住持の間があるべき場所に作られている。東西対象の位置にある書院の間が六畳であるのに対して、忘筌は手前座一畳を含む九畳と三畳の相伴席からなる十二畳となっている。 さらに詳しく平面図を見てゆくと、住持の間の南側のニ畳分が檀那の間となっているため、檀那の間十二畳となっていることが分かる。さらに忘筌に設けられた一間幅の床は仏間内に入り込み、手前座は縁の部分を室内化している。このように六室構成の禅宗方丈建築の形状を借りながらも、小堀遠州は方丈の中に忘筌を入れるために別な建築に作り変えていると言ってもよいだろう。広縁の西側に設けられた杉戸を開けると西面の縁に出るのではなく、踏石が置かれている。忘筌への客はここで地面に降りて、本堂西軒下の露地を歩かなければならない。軒下は赤味掛かった三和土で仕上げられ、直線状に飛び石が配されている。三和土とその先の庭との間には、やや幅広の直線状の縁石を張り、その先に黒い玉石を敷き詰めている。飛び石の先に有名な露結の蹲を置き、露地空間のアイストップとしている。蹲の足元は排水のために三和土を浅く抉っている。この処理に伴い、軒下に敷かれた縁石も、軽く櫛形に抉り落とされている。これは排水という実用上のことだけではなく、露結の蹲を中心とした領域を定義するために施した意匠であろう。
この蹲が置かれた場所から2段あがり、忘筌の西側の板間に至る。その際に、客は建物の面に嵌め込まれた明障子を潜らなければ席入りできないように仕掛けられている。これが草庵風茶室の躙口と同じ機能を果たしている。
床脇の手前座の壁は腰に明かり障子を嵌め込み、草庵風の意匠も取り入れている。これは忘筌が中庭を背にした場所に作られたことによって、採光が可能になっている。壁は余白を多く取った赤味を帯びた障壁画が描かれている。一間床の正面は張付壁で、墨蹟を架けるために余白の多い山水画が淡く、そして控え目に描かれている。角柱を用い、長押は床を含めて同じ高さで部屋中を巡らしている。長押の上は白い漆喰で印象的に仕上げられている。天井は板の木目が浮き出た「砂摺り天井」と称するもので、篩にかけて目を揃えた川砂に胡粉を混ぜ、木目に沿って木で摺り上げて胡粉で目止めしたもの。胡粉は貝殻を用いた白色顔料であるため、木目が白く浮かび上がってくる。これが長押の上部の純白と共に、この空間に清潔感を与えている。
今一度、忘筌から庭の方向を見る。縁先には土間から4尺6寸(1,393mm)の高さに中敷居を入れ、その上部を障子としている。土間から忘筌の床面まで1尺8寸(545mm)とすると、忘筌から見た障子下の開口部高さは2尺8寸(848mm)、横方向の開口幅を2間8寸(3,879mm)とすると、1:4.57の開口比となる。この開口部高さ2尺8寸は、正座した時の目の高さにほぼ一致する。
そのため忘筌を訪れた客は目の高さから下の西庭しか見えないようことになっている。その上で露結の蹲と寄燈籠のすぐ奥に低木を植えているため、庭の奥行きは感じられても近江八景の庭全体を眺めることはできないにしている。別々の石燈籠や層塔から笠、火袋、中台などを寄せ集めて作ったもの寄燈籠と呼ぶが、ここでは竿は宝塔の塔身、中台は五輪塔の火輪、火袋は宝筐印塔の台座、笠は五輪塔の水輪そして宝珠は五輪塔の風輪と空輪で構成されている。石の材質や色が異なったものを組み合わせて調和の美を求めているが、これも明障子で上部が蹴られることがないように高さ調整を行なった結果かもしれない。
また低木の手前には黒い玉石を敷き詰めることで、照り返しによって庭が明るくなり過ぎないように工夫しているように思われる。いずれにしても明障子は、席入りの際に躙口の役割を果たした明障子は、もともと西に面した忘筌の光量調整と視線制御のために設けられたと考えられる。
「大徳寺 孤篷庵 その4」 の地図
大徳寺 孤篷庵 その4 のMarker List
| No. | 名称 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|
| 01 | 大徳寺 孤篷庵 本堂 | 35.043 | 135.7399 |
| 02 | 大徳寺 孤篷庵 書院 | 35.0431 | 135.7397 |
| 03 | 大徳寺 孤篷庵 庫裏 | 35.0432 | 135.7399 |
| 04 | ▼ 大徳寺 孤篷庵 石橋 | 35.0434 | 135.7401 |
| 05 | ▼ 大徳寺 孤篷庵 山門 | 35.0434 | 135.7401 |
| 06 | ▼ 大徳寺 孤篷庵 延段 | 35.0432 | 135.7401 |
| 07 | 大徳寺 孤篷庵 外待合 | 35.0429 | 135.7401 |
| 08 | 大徳寺 孤篷庵 編笠門 | 35.0429 | 135.74 |
| 09 | 大徳寺 孤篷庵 南庭 | 35.0429 | 135.7399 |
| 10 | 大徳寺 孤篷庵 近江八景の庭 | 35.043 | 135.7396 |
| 11 | 大徳寺 孤篷庵 忘筌 | 35.0431 | 135.7398 |
| 12 | 大徳寺 孤篷庵 直入軒 | 35.0431 | 135.7397 |
| 13 | 大徳寺 孤篷庵 山雲床 | 35.0432 | 135.7397 |























































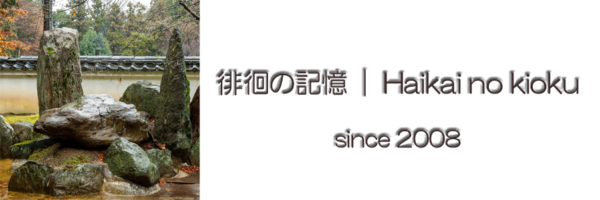

この記事へのコメントはありません。